今回は、団体保険のメリット・デメリットについてお伝えします。
会社によっては福利厚生制度で団体保険があります。
保険は定価が決まっており、割引をして加入することは基本できないのですが、団体保険では割引して加入することができます。
配偶者や子どもも入れる団体保険が用意されている場合もあります。
団体保険はメリットだけではなく、デメリットもあるので、活用する場合はしっかり確認しておきましょう。
YOUTUBEで全てを語っておりますので、是非ご覧ください。
動画は8分の長さがありますが、非常に濃い内容ですのであっという間に見ることができます。
動画の内容は文章でもここから下にまとめておりますので、こちらもご覧ください。
団体保険のメリット
まず、団体保険のメリットを整理していきます。
保険料が安い
企業が一括して加入者を管理することができるため管理コストが低く、広告宣伝費、保険を販売する人を介するコストも必要がないので、その分保険料を安く設定できています。
加入が容易
医師の診査が必要ない場合や健康の告知する範囲が少ないことで、加入しやすい場合もあります。
配当金が受け取れる
1年ごとに従業員の死亡率等の収支計算を行い、剰余金が発生すれば配当金を受け取れる場合があります。
団体保険のデメリット
次に団体保険のデメリットを整理していきます。
退職後継続できない場合がある
例えば、会社を辞めて、団体保険を継続することができない場合、持病を持っていては、新たな保険に入れない可能性があります。
退社後も継続利用できる団体保険もありますので、会社に確認しましょう。
継続できる場合も、一般的には年齢制限があり、例えば、75歳までは継続できるなど条件が決まっています。一生涯終身の保障を目的とする場合は向いていません。
1年更新型なので年齢が上がると保険料が高くなる
保険料が年齢が若い時には安く、年齢が上がると高くなります。
ただし、これはデメリットだけではなく、メリットの部分もあります。
若い時だけ、保険に加入する場合は、安い保険料で加入できるので、団体保険が向いている可能性があります。
一生涯保険料が変わらない保険商品もあるので、その方が良いという方は向いていないです。
民間保険の方が安い場合がある
健康な人、たばこを吸っていない人は民間保険の方が安い場合があります。
民間保険は、健康状態と喫煙の有無によって保険料が変わる保険商品が増えています。
「健康でたばこを吸っていない人」と「不健康でたばこを吸っている人」だとどちらが病気になるリスクが高いかというと、後者になりますよね。なので、保険会社によっては、健康な人、たばこを吸っていない人の保険料を割り引きしており、半額くらいになることもあります。
民間保険と団体保険どっちを利用するか
「民間保険と団体保険をどちらを利用した方がいいですか?」の僕のアドバイスは、保険の基礎知識を学んで、必要な内容や保障額を見極め、必要な保険が有利な条件で入れる方を選択するです。
コストを見ると団体保険の方が有利な可能性が高いと思います。
しかし、保険を考える時に、コストよりも重要なことがあります。
例えば、団体保険を活用すると、死亡保険が定価の3割安く加入できるとします。
団体保険にあるプランから1000万円の保障を選択し、お得に加入できたとしても、もし万が一が起きた場合、3000万円ないと家族が困ってしまうという状況に気づいていなかったらどうでしょうか?
保険を考えるときに一番大切なことは、自分に必要な内容や保障額を判断することです。
なので、ご自身の状況を把握し、自分で保険を学んでいる方は、コストや内容を比較して団体保険、民間保険から選択したらよいと思います。
保険の基礎知識の学び方としては、いくつか方法があります。
本を読む
保険の本はたくさん出版されています。
1冊だけ読むとたまたま読んだ本が偏った情報なこともあるので、複数冊読むことをお勧めします。
ブログやYouTubeを見る
本以上にたくさんの情報があり、本以上に誰でも発信できるので、正しい情報と間違った情報の区別がつきずらく、調べれば調べるほどよくわからなくなる方をたくさんみてきました。
いきなり、ブログやYouTubeを見るのではなく、本で体系的に保険の基礎知識を学んだ後、ブログやYouTubeを見ることがお勧めです。
ちなみに、保険の基礎知識を体系的に学べる動画とブログを作成していますので、よければご活用ください。
無料の保険屋さんに教えてもらう
多くの方がこの方法でやっているかと思います。
理由は、無料で楽だからです。
しかし、保険屋さんは当たりはずれが大きいです。また、団体保険を提案しても保険屋さんの手数料にならないので、ほとんどの方が団体保険を勧めてくれません。いろんなデメリットを伝えて、自分が扱っている商品をお勧めされることがほとんどです。
保険の知識の差がありすぎると、カモにされてしまいますので、無料の保険屋さんに相談する前に、本やブログ、YouTubeなどで保険の基礎知識は学んで活用しましょう。
有料のお金の専門家に教えてもらう
無料だと、保険を販売して手数料をいただかないとビジネスとして成立しないです。
有料の場合は、相談料はかかりますが、保険を販売する必要がないので、中立的な情報を得ることができる可能性が高いと思います。
有料のお金の専門家やお金のスクールも最近は増えてきましたが、有料だから必ず中立的な情報を得ることができるかどうかはわからないので、しっかりどの専門家に活用するか、見極めることが大切です。
まとめ
団体保険のメリット・デメリット、民間保険と団体保険どっちを利用するかについてお伝えしました。
団体保険のメリットは次の3つです。
●保険料が安い
●加入が容易
●配当金が受け取れる
団体保険のデメリットは次の3つです。
●退職後継続できない場合がある
●1年更新型なので年齢が上がると保険料が高くなる
●民間保険の方が安い場合がある
「民間保険と団体保険をどちらを利用した方がいいですか?」の僕のアドバイスは、保険の基礎知識を学んで、必要な内容や保障額を見極め、必要な保険が有利な条件で入れる方を選択するです。
無料で楽なやり方に走るのではなく、しっかり学んで考えて、自分に必要な内容や保障額を判断しましょう。
次回は、「県民共済のメリット・デメリット|安いだけを理由に選んだら失敗する」についてお伝えします。
「県民共済って安いからお得と聞くが本当?」よくある質問について解説していきたいと思います。
県民共済を安いだけを理由に加入すると失敗する可能性があります。
県民共済のメリット・デメリットを考えて、自分自身に合っている方法で実践しましょう↓↓↓






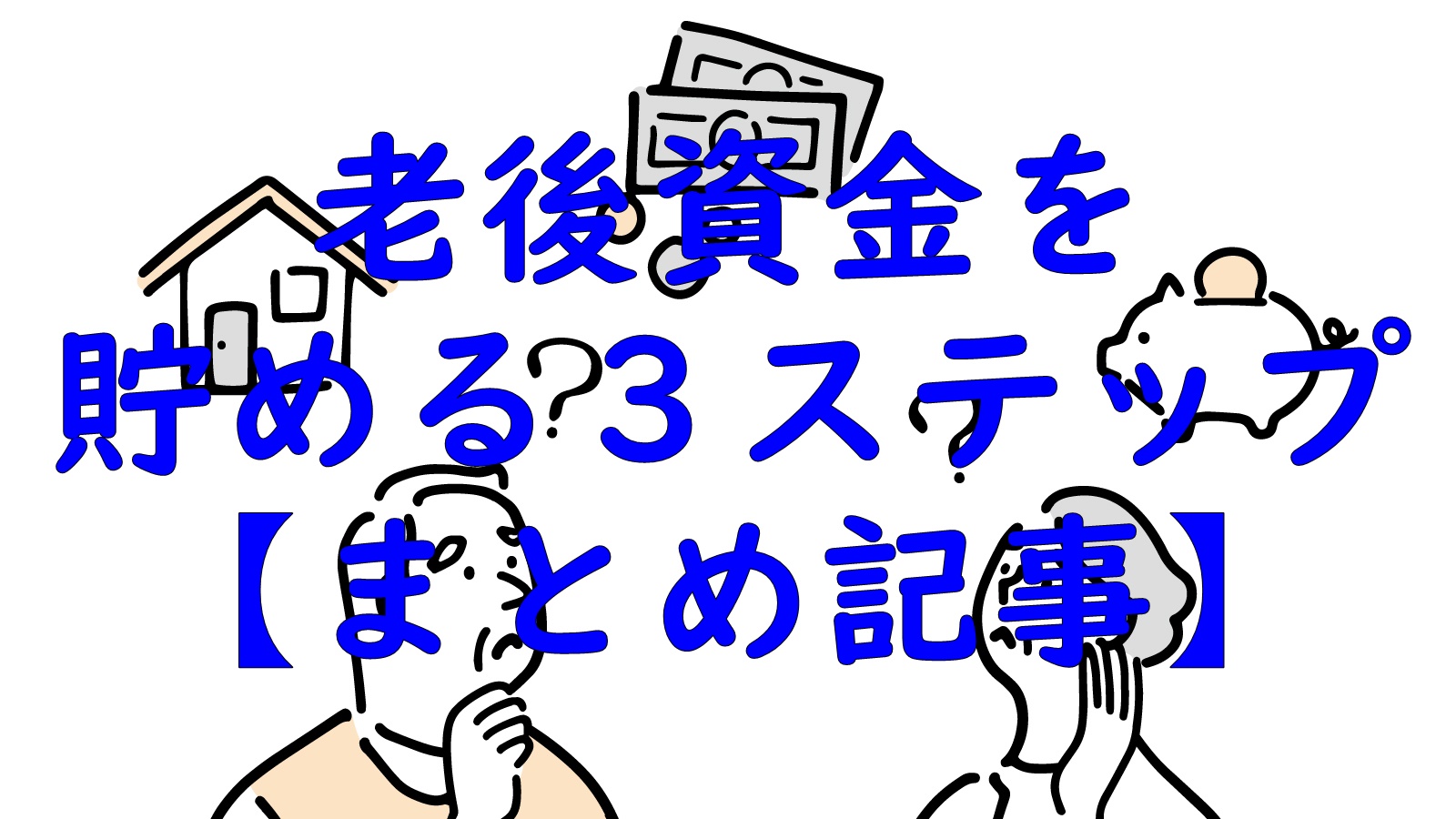









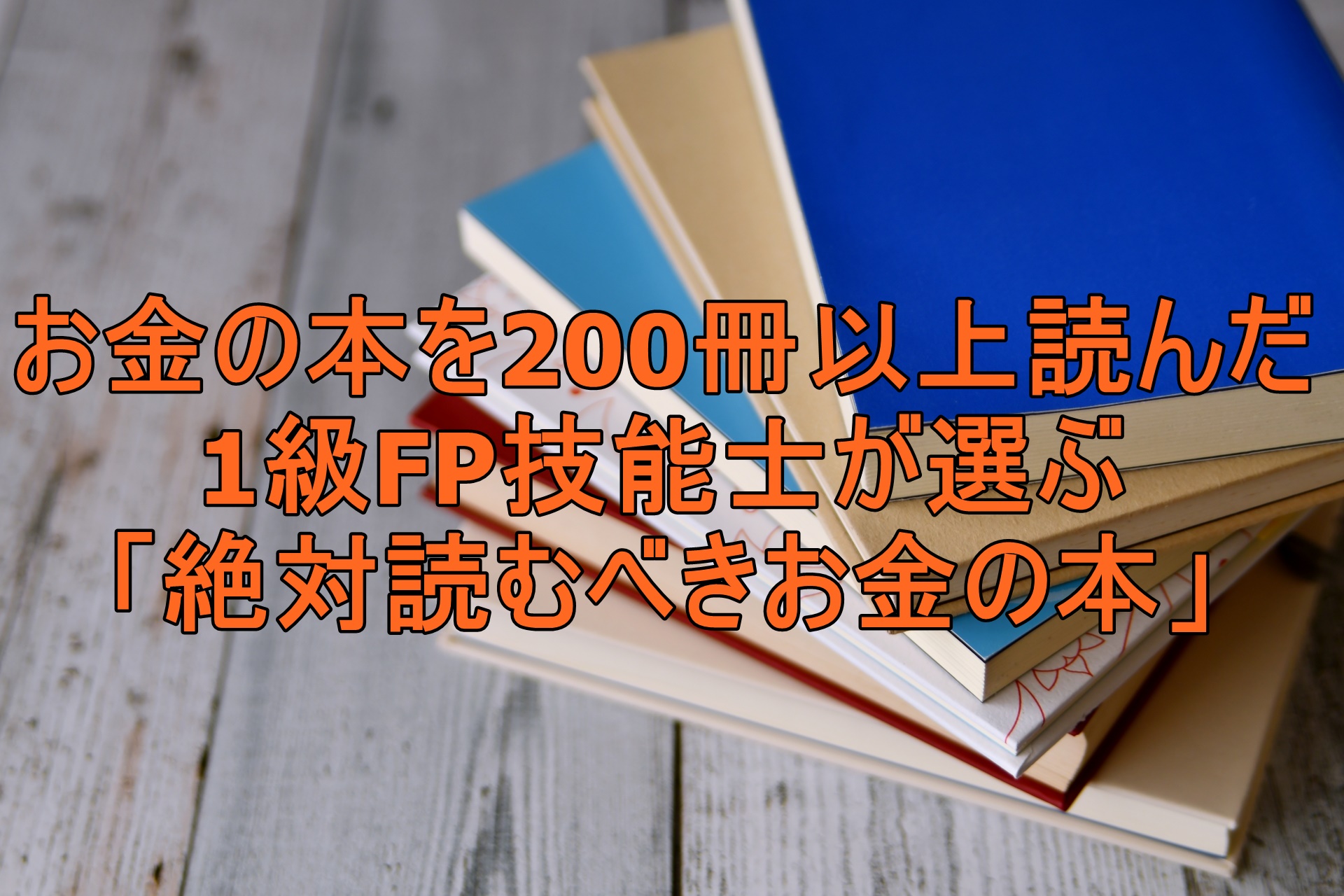

コメント
COMMENT