医療保険がいるのか、いらないのかを自分で判断できる考え方のポイントについて、医療保険・がん保険を安く最適化する方法についてお伝えをしていきたいと思います。
このブログを見ることで、自分自身で納得して、医療保険がいるのか、いらないのかを判断できるようになります。
YOUTUBEで全てを語っておりますので、是非ご覧ください。
動画は約15分の長さがありますが、非常に濃い内容ですのであっという間に見ることができます。
動画の内容は文章でもここから下にまとめておりますので、こちらもご覧ください。
目次
医療保険・がん保険が必要かどうかどう判断するのか?
「病気になったらお金がかかるから」「入院日数が短期化しているので日帰り入院でもお金がでる保険にした」などよく耳にしますが、医療保険に入られている方はどういう基準で入られていますか?
保険で必要な金額は「必要額―準備済額+気持ち」という式で表すことができます。
プラスになった方は、準備ができているので保険に入る必要はありません。
マイナスになった方は、準備ができていないので保険で備えることを検討しましょう。
必要額は、医療費です。
準備済額は、公的制度、預金などです。
そして、人間なかなか合理的には行動できない生物なので、余裕を持つかどうか、カツカツでいいのか、そういったところは最後気持ちで判断していきます。
準備済額
まず、準備済み額をみていきましょう。
準備できている額は、大きく2つになります。
1つが公的制度です。高額療養費制度、付加給付、傷病手当金があります。
もう一つが預金です。
皆さん病気になった時にどれだけ準備ができているでしょうか?
1つずつ見ていこうと思います。

高額療養費制度
医療費の自己負担部分は、ひと月あたりの上限金額が設けられています。
つまり、ひと月に医療費がどれだけかかっても基本的に健康保険の対象の治療であれば上限が決まっているということです。
その上限の金額は、標準報酬月額で決まります。ざっくり言うと月収のことです。

例えば、28万円から50万円の月収の方の場合、式が「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」になっています。
では、医療費が100万円かかる場合で計算してみましょう。
1,000,000-267,000円=733,000円
733,000円×1%=7,330円
7,330円+80,100円=87,430円
医療費が100万円かかっても、ひと月あたりの上限は87,430円ということです。
ここでの注意事項は、月毎の計算なので月がまたがって入院などする場合は別の計算になること、公的医療保険の適用外となる費用は対象外ということです。食事代、ベッド代、先進医療、自由診療など公的医療保険適用外となる費用は実費必要です。
付加給付
先ほどの高額療養制度に上乗せして、医療費をさらに払い戻してくれる制度が付加給付です。
付加給付は、利用できる人と利用できない人がいます。会社の健康保険の制度により異なります。
公務員、教職員、大企業に勤めている方は利用できる可能性があるので、ご自身の健康保険組合に確認をしてみてください。

例えば、先ほどと同じように28万円から50万円のところを見ていただくと、限度額が25,000円と書いています。
つまり、100万円医療費がかかったとしても、限度額25,000円の支払いで済むということです。最強の保険ですよね。
健康保険組合によって内容が異なりますので、皆さん是非自身の健康保険組合のHPで確認してみてください。
調べ方は
【1】ご自身の健康保険組合の名称をインターネットで検索
【2】健康保険組合のHP内に、「病気や大きな医療費がかかった場合」の項目をクリックします。付加給付があれば記載があります。

傷病手当金
病気や怪我で会社を連続して休んだ時、これまでの収入の約3分の2が支給される制度です。
まず3日間の連続する休業が必要です。その後も病気や怪我で休んでいるとなると、最長1年6ヶ月、例えば30万円の月収の方は約20万円が支給されます。
会社員の方の制度なので、自営業の方はありません。

支給の条件があります。
●業務外の事由による怪我や病気の休業
●仕事に就くことができないということ
●連続する3日間を含む4日以上仕事につけない
●休業した期間、給与の支払いがない
必要額の計算
次に、必要額をみていきましょう。
医療費、個室代、食事代や雑費などです。

医療費について、例えば、がんの入院と手術の場合、入院日数や手術の種類により異なりますが、100万円~200万円の費用がかかることがあります。
高額療養費制度でひと月約9万円、付加給付があれば、数万円が自己負担です。
しかし、これは健康保険対象の治療を行った時に利用できる制度なので、治療方法には健康保険の対象外、つまり全額自己負担の治療がいくつかあります。
全額自己負担の治療|①先進医療
海外や国内基礎研究、臨床研究で効果がある程度認められているものの、国が承認して保険適用にするほどの信頼性の高いデータが得られていない治療法です。
効果が証明されれば保険適用になります。
つまり、まだデータが十分ではないから先進医療にしているが、そのデータが集まってきて効果が証明されれば保険適用になって3割負担や高額医療制度が利用できる治療法です。

現在、先進医療で一番よく使われているのは、がんの治療の重粒子線や陽子線治療です。
年間約2000件行われており、それぞれ費用は約300万円です。
もしこの治療を行おうとすると、この300万円が3割負担も高額療養費制度も利用できませんので、実費必要になります。
全額自己負担の治療|②自由診療
健康保険を利用しないで自費で受ける診療で、海外では承認されているが日本では未承認の治療などです。

例えば、がんの抗がん剤治療にオプジーボというものがあります。
同じオプジーボを使う場合、悪性黒色腫、腎細胞がん、頭頚部ガンなどの治療として使えば保険適用で、3割負担、高額療養費制度を活用できます。
しかし、尿路上皮がんの治療として使えば、日本では自由診療になってしまいますので全額実費かかります。費用は約240万円(約2か月の想定治療期間)かかります。
つまり、オプジーボの場合、どんな癌の治療かによって健康保険の適用有無が決まっているということです。
病気に備える考え方
ここまで見ていただいて、考え方としましては3つあると思います。
1つ目が、医療保険で備える
2つ目が、貯蓄で備えて、自分で貯めたお金を医療費に備える
3つ目が、先進医療や自由診療など健康保険対象外で高額になる可能性がある部分のみ保険で備えて、あとは貯蓄で基本を備える。
先進医療や自由診療を民間の保険で補おうとすると、該当件数が現在非常に少ないので、保険料は数百円程度で安いです。
例えば、入院したら200万円もらえるという保険に月1万円払っているとします。もちろん10年間入院をしなかったら120万円払うわけですね。保険にかけるコストは無駄だったなとなります。例えば、入ってすぐ入院したら200万円もらえます。1万円支払って、200万円もらえます。
保険は、確率から言うと入ると損します。しかし、中には得をする人もいるのも事実です。
保険屋さんの中には、差額ベッド代や食事や交通費など医療費以外の雑費がかかるので、医療保険・がん保険を準備することを提案される方もいますが、差額ベッド代は必ずかかるお金ではないですし、食事、交通費など雑費は普段の生活でもかかるお金です。
預金がある程度ある方は、1か月入院しても約9万円なので預金で準備しておく方が合理的です。
会社員の方であれば、現在の給与の2/3の収入が維持できるので特にそうです。
しかし、医療保険やがん保険に入っていることで気持ち的に安心して生活ができるのであれば、お守りとして加入してもよいかもしれません。
医療保険・がん保険 比較時のポイント
保険を利用したいと思われた方に、保険の選び方のポイントをお伝えします。
様々な特約をどうつけるか
医療保険はいろんな種類、いろんな特約があります。
手術、通院、入院の一時金、女性がよくなる病気、怪我や骨折、三大疾病、払い込み免除などです。

これ以外にもたくさん特約があります。
つければつけるほど保険料は高くなります。
保険の基本的な考え方や気持ちから、本当に必要かどうか判断することが大事だと思います。
定義の確認
保険は、決められた条件でお金が出てきます。
この決められた条件、つまり定義を確認していくことが大事です。
例えば、三大疾病の定義を見てみましょう。
一般的には三大疾病というと、がん、急性心筋梗塞、脳卒中です。
保険でいう三大疾病の定義は、これ以外にも、がん、心疾患、脳血管疾患という定義もあったりします。
急性心筋梗塞と心疾患、脳卒中と脳血管疾患で何が違うのかを確認していきます。

まずは、心疾患を見てみましょう。
心疾患の患者数の内訳を見ると、急性心筋梗塞は心疾患の中の約2.5%ですね。
つまり、急性心筋梗塞で出ますよって言っている保険はこの2.5%、ここに当てはまったら出ますよということです。
心疾患の条件で出る保険は、不整脈、狭心症、心不全なども含まれます。
全然範囲が違いますよね。
次に、脳血管疾患の内訳を見てみると、脳卒中は脳血管疾患の中の約83.6%なので、脳卒中といえばこちら出るということですね。
脳血管疾患は、その他の部分も含めて出るということです。
これから入る保険や今入っている保険がどういった条件で出るのかしっかり確認しておく必要があります。
1入院の限度額
例えば、入院したら1日1万円出ますよという保険を考えます。
保険商品毎に様々な違いがあるのですが、その一つに1回の入院で何日まで受け取ることができるかという違いがあります。
30日型、60日型、120日型、180日型などです。30日型だと30日まで出るので、30日入院すると30万、60日にしても30万円ということです。
もちろん、出る日数を増やせば増やすほど、保険料高くなります。

今現在、入院の平均日数は、約33日くらいです。
「こんなに入院しているの?」と思う方もいらっしゃるかと思うのですが、実は見ておかなきゃいけない点があります。
極端に長い入院をする場合と短く入院する場合があるので、平均ってあんまり当てになりません。

長い入院する病気の例としては、精神及び行動の障害で、認知症、統合失調症、うつ病などですね。平均300日くらい入院しています。
また、神経系の病気で、アルツハイマー病も273日と長いですね。
脳血管疾患も77日です。60日を超えているのは、実はこれぐらいです。あとは基本的には60日以下です。
自分がどこに備えていくのかをしっかり考えて、何日型にするか決めていきましょう!
まとめ
医療保険がいるのか、いらないのかを自分で判断できる考え方のポイントについて、医療保険・がん保険を安く最適化する方法についてお伝えをしました。
自分自身で納得して、医療保険がいるのか、いらないのかを判断していきましょう!
次回は、「死亡保険に終身は必要ない!必要な保障額の計算方法と加入の仕方」についてお伝えします。
死亡保険が、必要なのか、不要なのか自分で判断できる考え方のポイント、必要な方には、死亡保険を安く最適化する方法についてお伝えをしていきたいと思います。
このブログを見ることで、自分自身で納得して死亡保険がいるのか、いらないのかを判断できるようになります↓↓↓
















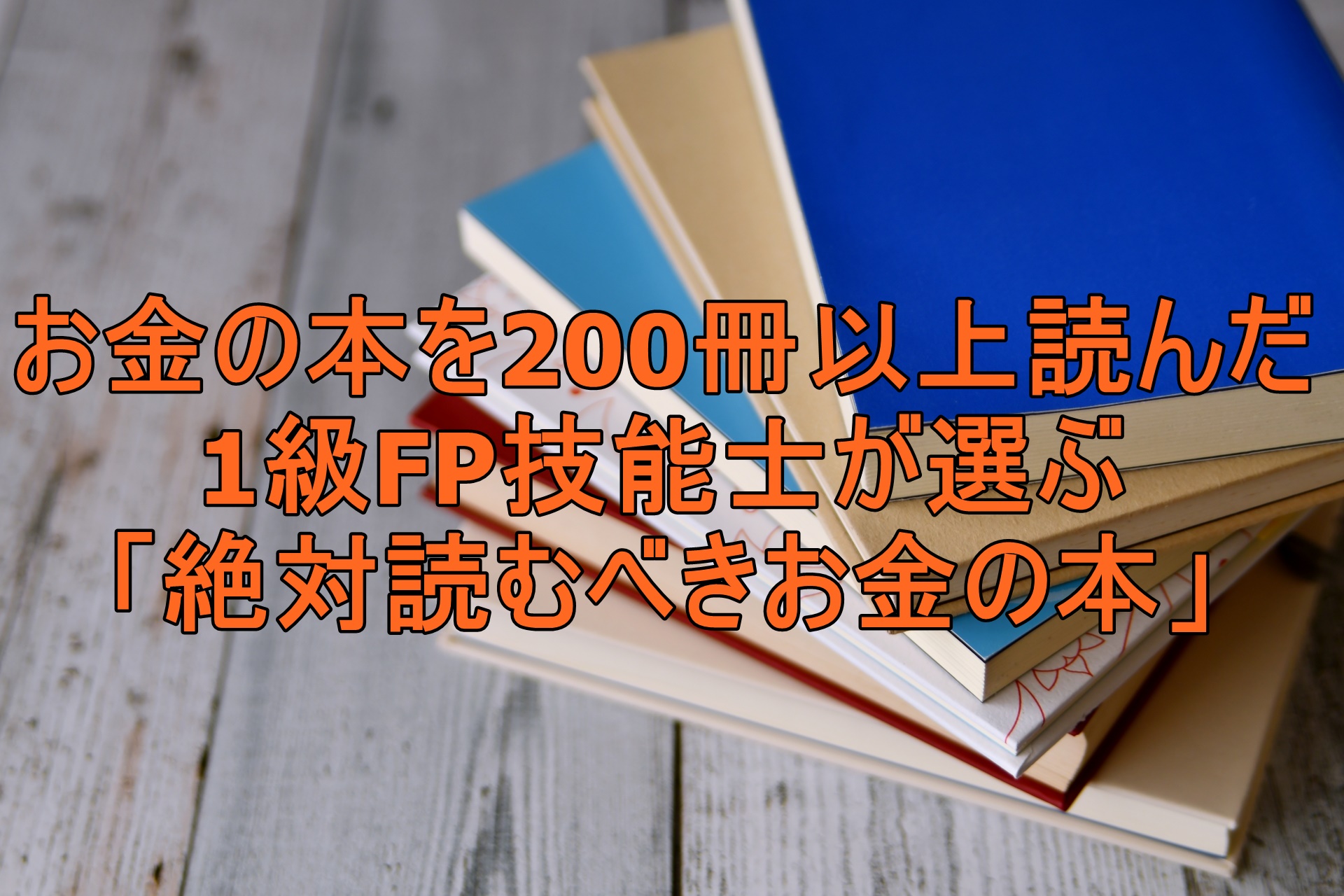

コメント
COMMENT