「親の介護をして大変だった。子供にはこんな想いをさせたくないので、介護保険に入りたい。良い保険ありませんか?」よくあるご相談です。
ちょっと待ってください!
介護のお金は介護保険で備えるのがベストではない場合もあります。
介護保険が、必要なのか不要なのかをご自身で判断できる考え方のポイントについてお伝えをしていきたいと思います。
このブログを見ることで、自分自身で納得して介護保険がいるのかいらないのかを判断することができるようになります。
YOUTUBEで全てを語っておりますので、是非ご覧ください。
動画は約16分分の長さがありますが、非常に濃い内容ですのであっという間に見ることができます。
動画の内容は文章でもここから下にまとめておりますので、こちらもご覧ください。
目次
介護の状況整理
まず、介護についての状況を整理してみたいと思います。
要介護認定者数と確率
国の介護保険制度で介護が必要だと判断されると要介護・要支援認定されます。
要介護認定者数が2000年は約189万人だったのが、2020年は約480万人になり、約2.5倍になっています。
要介護認定を受ける方がすごく増えてきていますね。
要介護・要支援になる確率は、75~79歳で8人に1人、80~84歳で4人に1人、85歳以上で2人に1人というのが日本の状況です。
高齢になるほど、増えてきていますね。
介護の原因
次に、介護が必要になる原因を見てみましょう。
1位:認知症 約18%
2位:脳血管疾患 約16%
3位:高齢による衰弱 約13%
1位の認知症はこれからも増えていくと言われています。
認知症の予想推移は2012年に約460万人、2030年に約830万人、2060年に約1154万人とされており、2060年には高齢者の3人に1人は認知症ということです。
認知症は超高齢化社会の日本では誰もがなりうるが、画期的な新薬が当面望めない、確立した予防がない状況です。

介護離職
そして、介護をお伝えするのに欠かせない内容として、介護離職があります。
誰が介護をしてるのかということです。
家族・親族による介護が約7割、事業者・その他による介護が約3割と言われています。
つまり、家族と親族がいるから今の介護が成り立っていて、実は介護が理由で離職する方が毎年10万人います。
仕事をしながら介護している方も、約69万人います。
そして、親が子や配偶者に迷惑かけたくない気持ちはもちろんあるのですが、子供の気持ちとしては、「今までお世話になってて、ここで親孝行をしなかったらいつするんだ」ということで親の介護をされている方が多いのではないかと思います。
介護には費用と時間がかかります。
介護に時間を割いたり、仕事を辞めたりするので、収入が落ちてしまう可能性もあります。そして、親が70代80代ということは、子供は50代になっているので、ちょうど結婚して子育てされている方だと子供の教育資金がかかる時期でもありますし、仕事もすごく忙しい時期になってくるので、大変な社会問題になっています。
介護の費用はどのくらいかかる?
介護の費用を考える上で、まず押さえておきたいのが公的な介護制度、介護保険ですね。
冒頭、要介護認定のお話をしましたが、認定された要介護度により支給限度が違います。お金がどれだけ支給されるかが違うということですね。
支給限度額を超えた場合は自己負担になります。
そして、こちらは現金でお金をもらえるのではなくて、介護サービスを利用したらその割引を受けることができる制度になっています。
基本自己負担は1割で、9割は介護保険から出ます。

そして、公的介護保険サービス以外は全額自己負担になります。
何でもかんでも使えるわけではなくて、日常生活費(医療、居住、消耗品) 、住宅改修、福祉用具、介護施設費、家事代行、配食サービスなどは自己負担になります。
介護保険の支給限度額
では、どのくらい支給限度額があるのかを見てみましょう。
要支援1、2、要介護1から5があり、右に行くほど介護度が高くなります。

それぞれに支給限度額の上限が決まっています。
例えば、要支援1だと約60万円の年間支給限度額があり、その1割負担なので皆さんが仮に要支援1になったとすると、自己負担は6万円で60万円の介護サービスを受けることができるということです。
仮に要介護5だと430万円支給限度額になりますので、自己負担は1割負担なので、43万円で430万円の介護サービスを受けることができます。
介護費用の平均
次に、介護費用の平均データを見てみましょう。
月々の出費は平均約78,000円です。
そして、バリアフリーにしたり、車椅子を購入したりするなど一時的な費用は、平均69万円です。
介護の期間の平均は、4年7ヶ月です。
これを計算すると、毎月78,000円×4年7ヶ月+一時金69万円で425万円となります。

ネットを見ると、500万円で足りると言われていることもありますが、本当でしょうか?
この月々の出費の78,000円は、在宅介護も含んでいます。
実際7割が在宅で、1割ぐらいが施設で介護をうけていると言われています。
もちろん施設に行った方が、お金がかかりますので、そのあたりはあくまで平均として見る必要がありますね。
介護施設の費用
介護施設に入ると結構お金かかりますよね。
どのくらいかかるのでしょうか?
要介護者向けの施設として代表的な2つについて、今回はお話します。
特別養護老人ホームと介護付き有料老人ホームです。

特別養護老人ホームは要介護3以上の人でないと入ることができません。
特徴は安いことです。介護保険が適用できるので5万円から利用することができます。
その代わり結構埋まっている場合が多いので、地域によっては順番待ちの状況とところもあります。
もう一つが、介護付き有料老人ホームです。
こちらは要支援1から利用することができますが、高いですね。
本当にピンキリで約15万円ぐらいから約35万円、もっと高いのもあったりします。
ポイントとしましては、
●この要介護者向け施設に入ると、施設職員が24時間体制で介護サービスを提供してくれます。
●認知症や見取りにも対応してくれます。
●重度化しても、最後まで利用することができ、途中で追い出されるって事がないということです。
介護の費用は500万円で足りる?
ここまでの話を踏まえて本当に介護の費用は、500万円貯めとけば足りるのか、考えて見ましょう。
まず、介護をするにしてもしないにしても、日常生活費がかかると思います。
食べたり、飲んだりする費用ですね。
安くても3,000円かかるのではないかということで3,000円と仮定すると、月9万円ですね。
そして介護の費用が月78,000円ですね。
居住費が5万円から35万ぐらいかかります。
それに対して収入は、人それぞれ違うと思いますが、夫婦の年金収入の平均が、約22万円です。
特別養護老人ホームに入れたら足りるかもしれません。
家族が見てくれたら足りるかもしれません。
有料老人ホームに入ったらどうでしょうか?
平均4年7ヶ月より期間が長かったらどうでしょうか?

本当に500万円で足りるのかということですよね。
平均の4年7ヶ月で見るのではなくて、10年ぐらいで見て、1000万円用意しとこうかという人もいると思います。
特別養護老人ホームではなくて、有料老人ホームに入りたいという方であれば、かなりお金を用意しとかなきゃいけないですね。
人それぞれ準備する額は変わってきます。ご自身が介護状態になったら、どういったところでどういうふうに介護を受けたいかを実際にイメージをしていただいて、金額を設定していきましょう。
お金が準備できたら大丈夫?
これまでお金の話をしましたが、では、お金があれば大丈夫なのかというと、そうではないリスクがあります。
それは、認知症による資産凍結リスクです。
皆さん聞かれたことはありますでしょうか?
認知症になるといろいろ困ることがあります。
預貯金は解約することができなくなります。
有価証券も売却できなくなります。
土地や建物も売却できなくなります。
生命保険も解約できないです。
遺言書も作成できなくなります。
生前贈与もできなくなります。
つまり、生活資金の不足になる可能性や相続対策ができなくなる可能性があります。
せっかくお金があるのに引き出すことができなかったりするんですよね。

これを解決するために、成年後見制度っていうのがあります。
弁護士さんや司法書士さんがついて、弁護士さんや司法書士さんの許可をもらうことで、認知症になった方の財産を使用できます。
家族が勝手に認知症になったおばあちゃんの口座から預貯金を引き出すことは、できなくなってくるということなんですね。
つまり、お金があるのに生活資金が不足する可能性があるということです。
もしくは思い通りにお金を使うことができなくなるリスクがあるということですね。
お金を準備するだけでなく、お金を使える状態にしておくこともすごく大事だと僕は考えています。
例えば、認知症になり成年後見制度を活用する前に、元気なうちに任意後見や家族信託等で資産の凍結を回避したり、事前に家族の話し合いをしていくことが大事だと思います。
任意後見や家族信託について、ここで詳しくはお伝えしないですが、資産凍結を解決するための一つの手段となっています。
そして、成年後見制度がつくと、値動きがある有価証券は解約される可能性が高いです。僕のお客様の中には長期運用をしながら、その資産の取り崩しをして老後の生活をしている方もいらっしゃいます。認知症になっても資産の取り崩しができるように家族信託口座を作るということも一つの手段になります。
そして、生命保険を活用する場合は気を付けたいポイントがあります。
例えば介護状態になり、保険から介護給付金が出ました。
介護になったのでお金が1000万おりてきました。
しかし、受取の口座が本人になっていると、認知症になるとそのお金使えないですよね。
これを回避するために、介護保険の中に、指定代理人といって、契約者以外に家族の方などが代理で給付金を請求できる制度があります。通常、給付金の請求は代理でできますが、その入金はご本人になります。
しかし、その入金も指定代理人の家族などに入金できる保険商品もあるので、介護保険を活用するのであれば確認して入られた方がいいと思います。
介護のお金の備えはどうやってする?
次の3つが考えられます。
①預金で備える
②保険で備える
預金で備えるのか、保険で備えるかは次の章で保険で備えるメリット・デメリットをお伝えしますので、それを見て、保険で備えた方が良いか、預金で備えた方が良いか判断しても良いかもしれません。
③資産運用で備える
例えば、元気でも介護でも不動産や株式の配当金などで、お金が出てくるようにしておけば、介護でも、元気でも使えるお金になります。
僕はこれを目指しています。
介護を保険で備えるメリット
保険で備えるメリットは下記2点になります。
①老後後半に介護費用を残しておけること
強制的に保険で積み立てをしていますので、介護になった時に出てくるお金として、強制的に残しておけるというのはメリットかなと思います。
②介護終身年金を活用し、いつまで続くか分からない不安に対応できること
介護をしたことがある方に何が不安かと聞くと、この介護がいつまで続くかわからないことがすごく不安に感じている方が多いです。
そういった方に対しては、終身年金といって、介護になったら亡くなるまでお金が出続ける保険の受け取り方がありますので、活用してもよいかもしれません。
介護を保険で備えるデメリット
保険で備えるデメリットは、3つあります。
①保険料が高い
こちらは想像がつくと思いますが、保険の仕組みから考えると、誰もが高齢とともに要介護の状態になる可能性が高いのであれば、手頃な保険料で手厚い保障を受けることは、なかなか難しいというところですね。
②老後使えない保険になる可能性がある
保険は、契約した時に全ての条件が決まります。
医療技術が進歩したり、社会状況が変化したり、介護制度の見直しがあった時でも保険の条件は変わりません。
例えば、要介護2で今介護の給付金を受け入れるような保険に入ったとして、要介護認定の基準が変わったらどうなのか?保険会社が条件を変えてくれるのかは、そうなってみないと分かりません。
③元気な老後の生活には使えない
保険ですので介護になったら給付金がもらえる商品になっていますので、介護にならなかった時にご自身の旅行や生活費などに使うことができないお金になります。
介護保険を選択するポイント
民間の介護保険を活用する方は、次の3つのポイントを意識して自分に合った商品を選んでみてください。
①支払い要件
保険ですので介護のどんな状態になったらお金をもらえるのかをきっちりと確認しておくことが必要です。
例えば、要介護1なのか2なのか、それとも保険会社の独自の要件があるのかなどですね。
②支払いの期間
先ほどお話した、亡くなるまで出続ける終身年金なのか、それとも5年や10年など期間限定の有期年金なのかも確認が必要です。
③継続要件
大きく2つに分かれます。
1つ目が、改善したら止まるというパターンですね。
例えば、要介護2で介護年金が出て、要介護1になった時は介護年金が止まってしまうパターンです。
2つ目が、1回認定されれば回復しても定められた期間まで継続給付があるパターンですね。
要介護2で保険給付がある介護保険で、要介護2に該当し介護年金を受け取ると、その後、要介護1になろうが要支援になろうが定められた期間まで継続的に給付されるということです。
こちらも注意しておきたいところですね。
介護を考える上でもっとも大切なこと
よくある介護する子の後悔として、親の想い(介護方針、看取りの場、延命治療など)を聞き、元気な頃から家族で話し合いをしていればよかったということをよく聞きます。
もちろんお金のことも聞くこともありますが、これが一番多いです。
なので、預金や保険などを活用して、お金の準備をしておくことももちろん大事ですが、そのお金を使える状態にしておくことも大切です。
準備しただけで、自由に使うことができなかったら意味がないので、しっかり自由に使うことができる状態にしておきましょう。
そして、一番大事なのは元気なうちに家族で話し合いをしておくということですね。
まとめ
介護のお金は介護保険で備えるほかにも選択肢があります。
介護保険が、必要なのか不要なのかをご自身で判断できる考え方のポイントについてお伝えをしました。
自分自身で納得して介護保険がいるのかいらないのかを判断しましょう!
次回は、「外貨建て・変額保険とiDeCo・NISAを比較!保険で貯蓄はやめたほうがいい理由をわかりやすく解説」についてお伝えします。
皆様から保険に関して最も多い質問「貯蓄保険がいいんですか?それともiDeCoやNISAがいいんですか?」について解説です。
それぞれのメリット・デメリットを確認して、どう貯蓄をしていくか判断しましょう↓↓↓






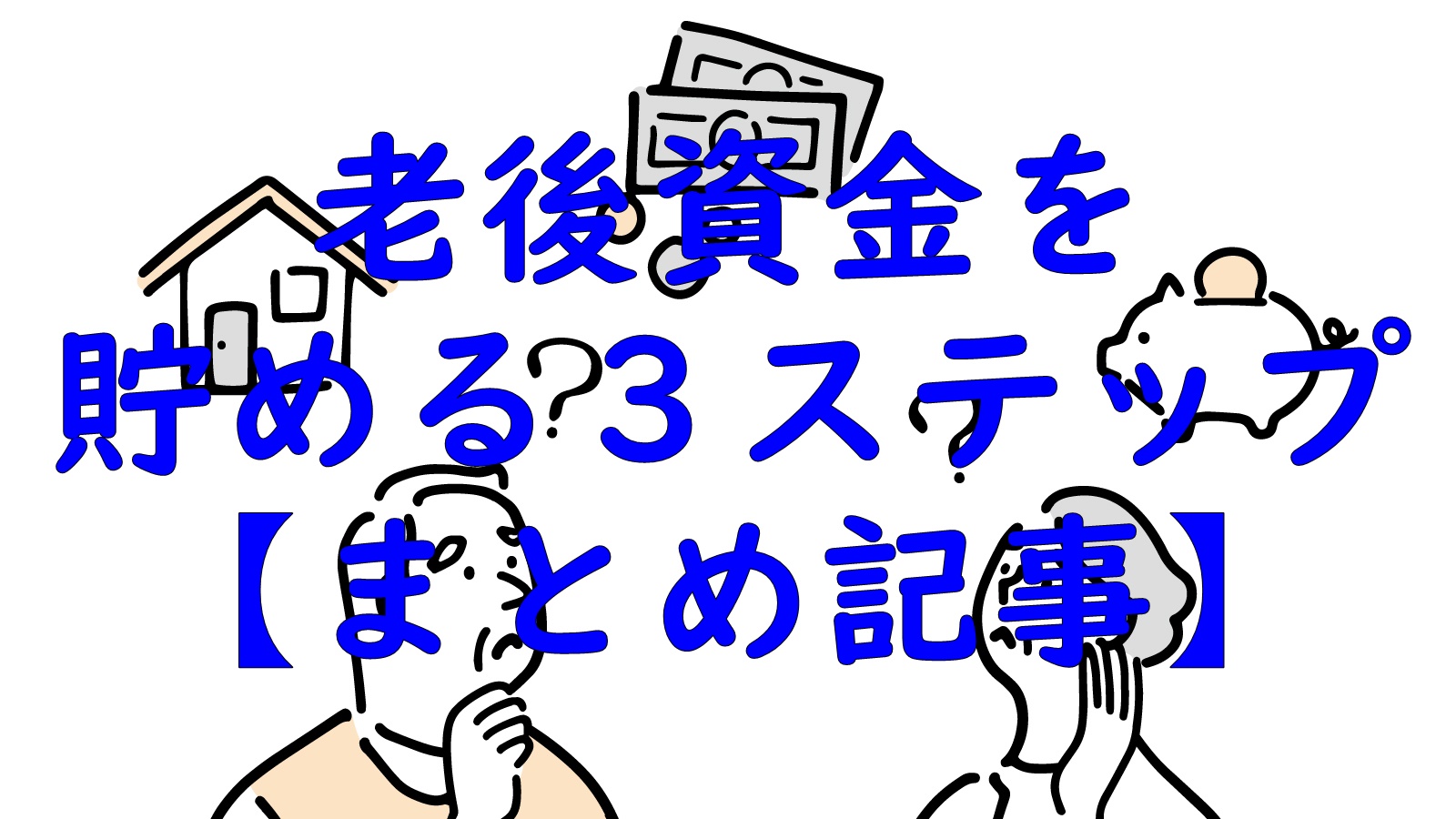









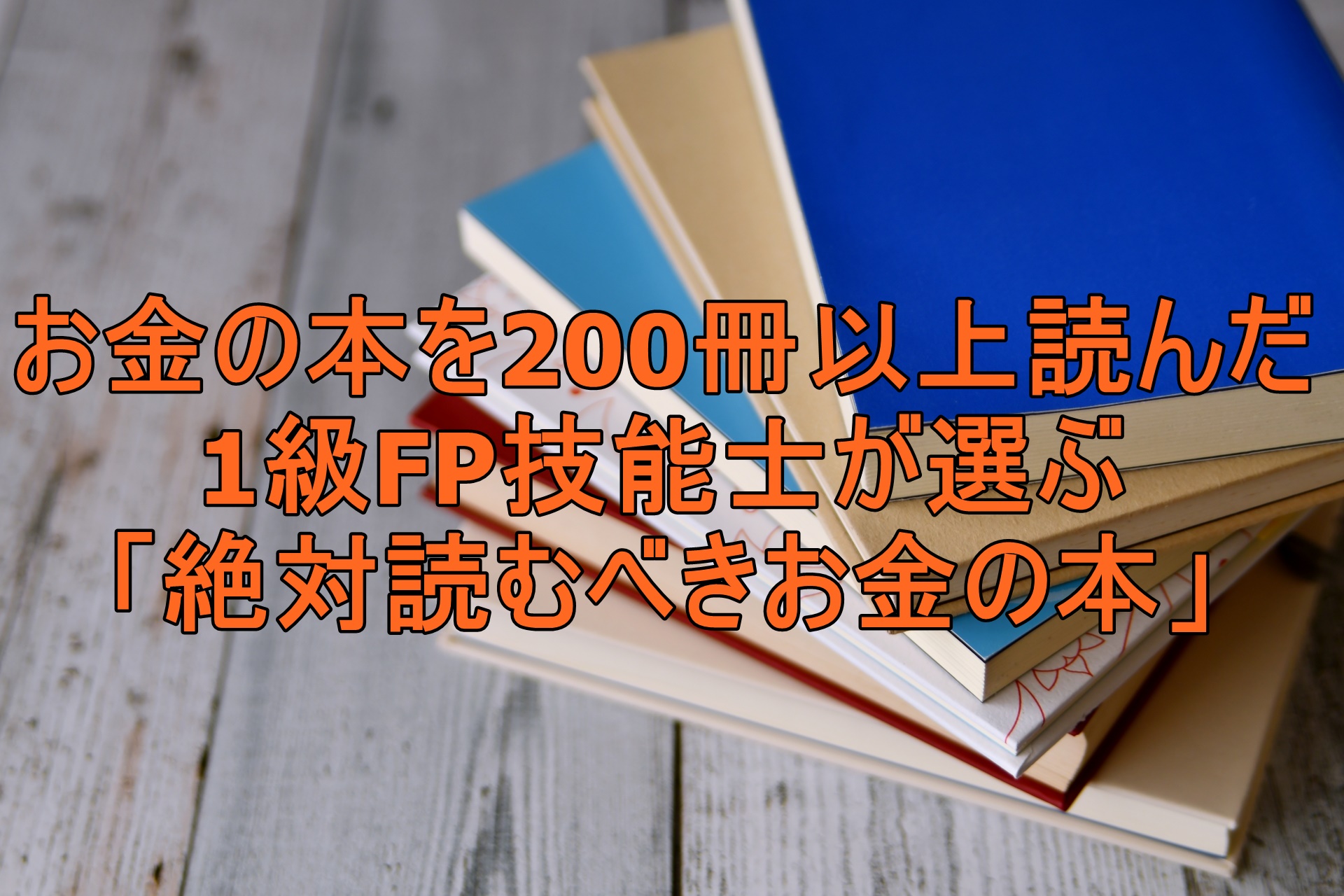

コメント
COMMENT