自動車保険の内容は、担当の方にお任せしていて、言われるがまま加入している方が多いと思います。
言いなりでは自分に合っている保険に加入することは難しいです。
少し手間をかけることで、保険料を抑え、自分に合った自動車保険を選択できます。
その具体的な方法について、複数回に分けて解説しています。
順番にご連頂くと理解しやすいです。
今回は、これまで自動車保険の仕組みや内容を学んだ上で、「自分に必要な条件を検討する」についてお伝えします。
リスク管理の考え方は人それぞれ異なりますので、保険の基本を押さえて、自分で考えて見直しをしていきましょう!
YOUTUBEで全てを語っておりますので、是非ご覧ください。
動画は約15分の長さがありますが、非常に濃い内容ですのであっという間に見ることができます。
動画の内容は文章でもここから下にまとめておりますので、こちらもご覧ください。
目次
自分に必要な条件を検討する
人によって必要な条件は違います。
保険料の安さだけで決めてしまい、必要なときに必要なお金がでないと意味無いので、まずどの内容が必要なのかを考えてから、保険会社を比較しましょう。
ステップ①基本項目の必要性を考える
基本となる各項目が必要かどうか、必要ならどのくらい備えるか考えましょう。
基本項目について分からない方は下記ブログを先にみてくださいね。
https://isoyama-fp-office.com/auto-insurance-basic-coverage/
●対人・対物賠償責任保険:基本的には無制限で設定でしたね。
●人身傷害補償保険:3000万円~無制限で設定できます。
基本の補償になっている保険会社とオプションの保険会社があります。
●車両保険:必要な場合は、一般か限定か、免責の有無を検討しましょう。
ステップ②特約の必要性を考える
保険会社によって名前や内容が違うので注意しながら、必要なものを検討しましょう。
代車費用、弁護士費用、個人賠償責任補償などですね。
特約の内容について分からない方は下記ブログを先にみてくださいね。
【1級FPが解説】自動車保険の特約には、どのようなものがある?自転車事故も補償されるって本当?おすすめの特約をわかりやすく解説
特約やロードサービスなどその微妙な違いを売りにしている保険会社もありますが、その違いが絶対に必要であれば、その保険会社を選択してもよいかと思います。そうでなければ、基本的な条件を統一して比較しましょう。
ステップ③保険料を安くする条件や活用法を確認する
保険は設定する条件や活用法で保険料が変わってきます。
知っているか知らないかだけで保険料を安くすることができる可能性があります。
①運転者の範囲
まず、運転者の範囲を考えていきましょう。
運転者の範囲は下記4つに分かれます。
●本人のみ
●本人と配偶者
●家族(本人と配偶者と同居の親族と別居の未婚の子)
●限定無し
運転者の範囲を限定すればするほど保険料が安くなります。
運転者の範囲以外の方が運転して事故が起きると保険が使えないので注意が必要です。
②運転者の年齢条件
次に、運転者年齢条件を設定していきましょう。
運転者の範囲の中で、最も若い方の年齢に合わせて設定します。
年齢条件の区分は保険会社により異なりますが、下記のように設定されていることが多いです。
●年齢を問わず補償
●21歳以上補償
●26歳以上補償
●35歳以上補償
年齢条件が適用されるのは、一般的には、契約者、配偶者、同居の親族のみです。別居の親族や友人知人などは適用外となり、年齢条件に関係なく補償されます。
例えば、夫婦と同居の子供が同じ車を運転する時は、子供は同居の親族なので、子供の年齢に合わせて設定が必要です。子供が22才であれば、21才以上の区分になります。
夫婦と別居の子供がいて、子供が帰ってきた時だけ車に乗るような場合は、子供は別居の親族になるので年齢条件に関係なく補償されます。ご夫婦が50代であれば、35才以上の区分で設定できますね。
一部の保険会社では、運転するすべてのドライバーを対象にしていることもあり、保険会社毎に異なるのでご自身で確認しましょう。
③使用目的
車の使用目的によって、保険料に違いがでてきます。
業務使用、通勤通学使用、日常レジャー使用の3つに分かれている保険会社が多いです。
使用目的は年間を平均して月15回以上の使用状況で判断します。
日常レジャー使用は、業務使用と通勤通学使用に該当しない方です。
普段電車通勤だが、たまに天候が悪い時だけ車を使う場合、日常レジャー使用でOKです。
例えば、ほぼ自宅で仕事をしており、仕事で車を乗るのは週3日くらいの場合、年平均して月15日以上仕事で使用しないので日常レジャー使用でOKです。
日常レジャー使用にしていて、業務中事故にあっても補償はされるので大丈夫です。
保険を請求する際に、使用実態を聞かれる可能性はあります。
申告している内容が異なると保険金が支払われないことがありますので、うそはだめです。
④セカンドカー割引
すでに契約している自動車保険の等級が11等級以上の方が、2台目を購入する場合、通常は6等級ですが7等級からスタートできます。
2台目の車と1台目の車の所有者や主な運転者が個人であり、同じもしくはその家族である必要があります。
例えば、お父さんの等級が11等級以上、同居の息子さんが初めて車を購入する場合などで使えますね。
⑤全車料率一括割引
2台以上の車を同じ保険会社にして、1つの保険証券にまとめると台数に応じて1~6%割引になります。
契約者を同じにして、同じ保険会社に揃えて1つの証券にまとめることが条件です。
自動車保険の満期をそろえ、契約者がまとめて支払いする必要があります。
家族で別々の保険会社にしている場合、検討してみましょう。
⑥免許証の色
免許証の色はゴールド、ブルー、グリーンがあり、ゴールド免許の場合8~10%割引があります。
契約者は、保険の申込をして保険料を支払う人です。
被保険者は、主に使用する人です。被保険者の免許証の色で割引が決まります。
家族で1台の車を使っている場合、奥様がゴールド免許、ご主人がブルー免許の場合、ゴールド免許をもつ奥様を被保険者とすると安くなりますね。
⑦大口団体割引
大企業や官公庁などで働かれている方は所属企業の団体保険を活用しましょう。
通常より15~30%割引になりますのでお得ですね。
⑧ダイレクト型保険を活用する
自動車保険には、担当者がいて様々な相談ができる代理店型と自分でネット申込をするダイレクト型に大きく分けられます。
代理店型は、一般的に大手損害保険会社になり、東京海上日動火災、あいおいニッセイ同和損保、三井住友海上火災、損害保険ジャパンなどです。
ダイレクト型は、SBI損保、ソニー損保、セゾン自動車火災、チューリッヒ保険などがあります。
一般的にはダイレクト型の方が、保険料が安いです。
代理店ならではのメリットがいくつかあるので、それが必要なら保険料が高くても代理店で、不要なら保険料が安いダイレクト型を選択されたらよいかと思います。
詳しく知りたい方は下記ブログを見てみてください。
また、ダイレクト型では新規割といって1年目だけ保険料をさらに安くしてくれる割引があります。
手間はかかりますが、これを活用し1年毎にダイレクト型の保険会社を乗り換えすることで保険料を安くすることもできます。
保険会社を変える手間はありますが、例えば、ソニー損保とSBI損保を交互に契約するなどでメリットが出る場合があります。
もちろん、使い方や継続の割引など比較して検討してくださいね。
⑨長期契約を活用する
自動車保険は基本1年単位での契約になっていますが、2年以上の長期での契約もあります。
長期契約を扱っている保険会社と扱っていない保険会社があります。
代理店型では扱っているケースが多く、ダイレクト型では扱っていないケースが多いですね。
長期契約にするメリット
●保険料が割引になる可能性がある
●毎年更新する必要がない
例えば、3年契約の場合、3年間は更新する必要が無いので手間が省けますね。
●事故を起こしても次の更新時まで保険料が上がらない
1年契約の場合は、事故を起こして保険を請求すると翌年から等級が下がります。
例えば、3年契約の場合は、保険を請求しても、3年間は保険料が当初決まった金額から変更がありません。
長期契約にするデメリット
●契約期間内は条件が安くなる契約変更ができない。
契約時に免許証の色がブルーだった方が、翌年ゴールドになって割引が効く場合も、長期契約ではゴールド免許の割引を受けれません。
次回更新時に、ブルーからゴールド免許になる可能性があるのであれば、長期契約にしない方がよいかもしれませんね。
●何度も事故を起こすと契約更新時に一気に等級が下がる
3年契約で当初10等級の方の場合で考えてみましょう。
3年間無事故の場合は、4年目の更新の時は、3等級上がり13等級になります。
3年間の間に複数回事故を起こした場合、例えば、1年目は無事故、2年目と3年目に3等級ダウン事故をした場合、1年目で+1等級、2,3年目で-6等級なので、4年目の更新時は5等級なります。10等級から5等級に一気に等級が下がり、保険料が上がってしまいます。
⑩乗らなくなったら中断の手続き
家族で1台の車にすることになったので車を手放すなどの場合、車に乗らなくなったので自動車保険を解約すると思います。普通に解約してしまうと、次に再び車に乗ることになった時、自動車保険を契約すると6等級からスタートしてしまいます。
この場合、中断の手続きをすることで、今の等級を保存できます。
今の等級を保存できる期間は通常10年、妊娠による中断は3年です。
その他
一部の保険会社では使用地域や走行距離で保険料が変わる仕組みにしているところもあります。
まとめ
今回は、これまで自動車保険の仕組みや内容を学んだ上で、「自分に必要な条件を検討する」についてお伝えしました。
人によって必要な条件は違います。
保険料の安さだけで決めてしまい、必要なときに必要なお金がでないと意味無いので、まずどの内容が必要なのかを考えてから、保険会社を比較しましょう。
リスク管理の考え方は人それぞれ異なりますので、保険の基本を押さえて、自分で考えて見直しをしていきましょう!
その他の自動車保険の見直しの具体的な方法については、下記にまとめておりますので、是非ご覧いただき、実践してみてください↓↓↓






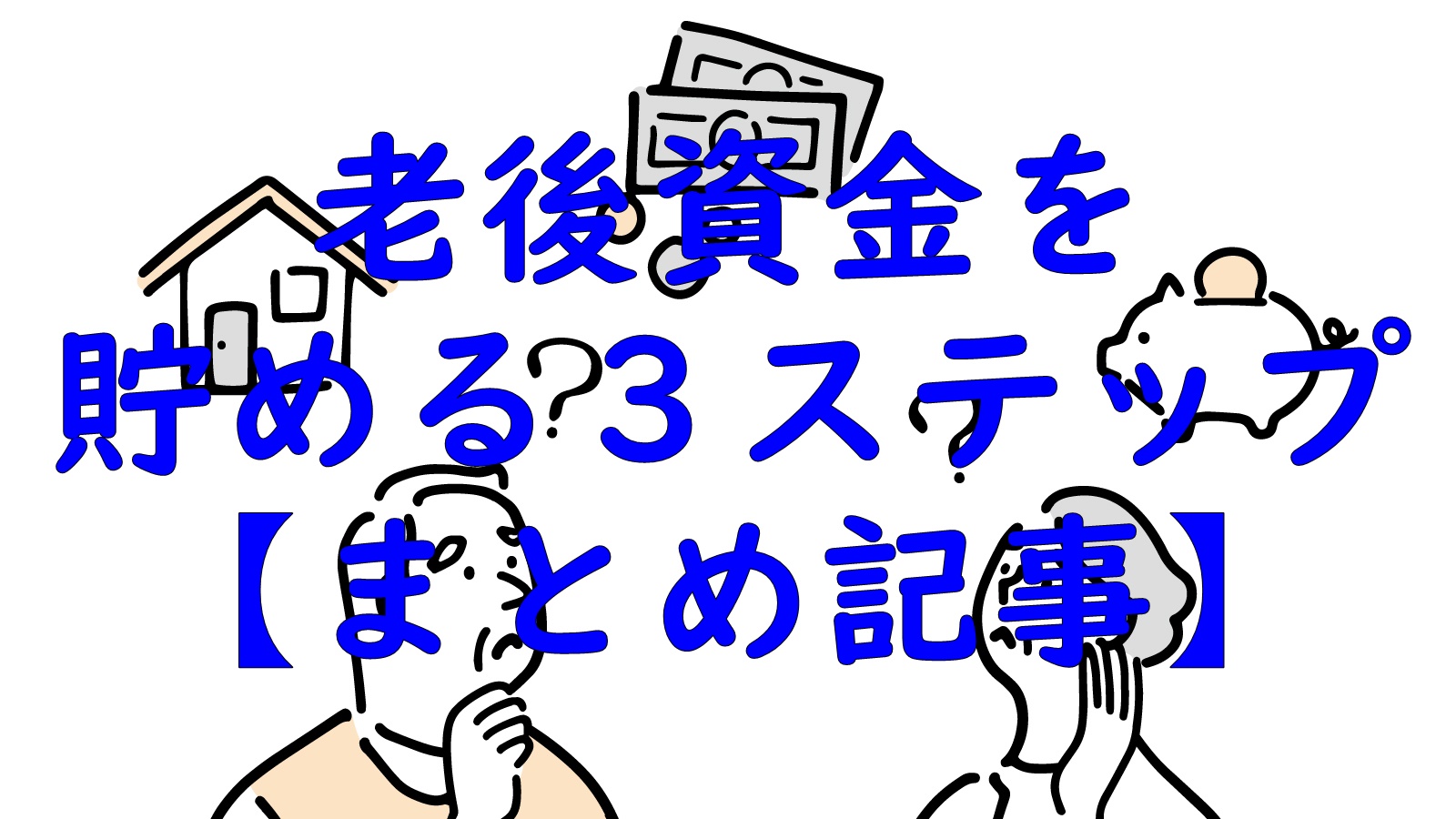









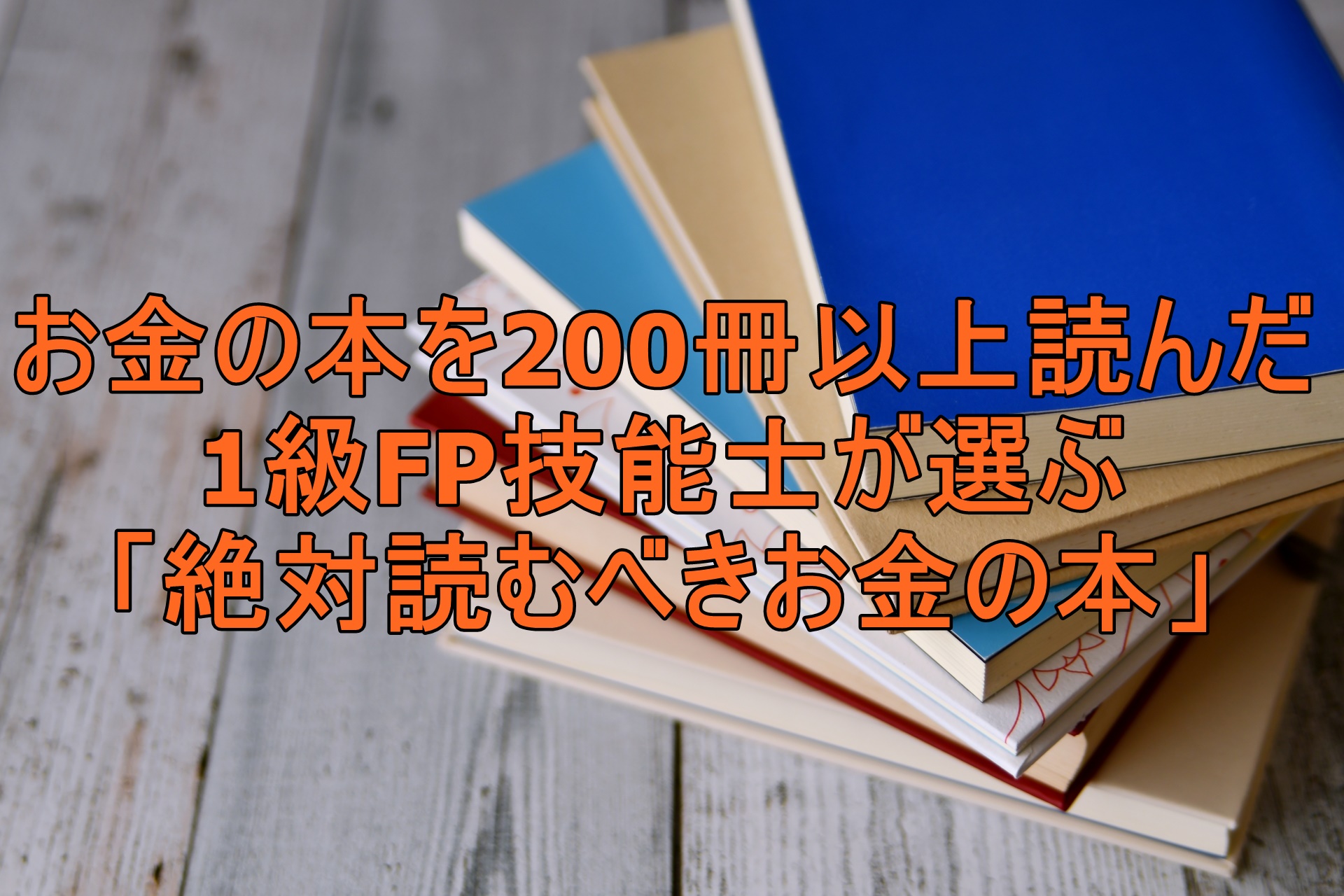

コメント
COMMENT